- 【PR】記事内に広告を含む場合があります。
子どもは何歳からおもちゃを片付けられる?楽しく習慣化するコツと年齢別の教え方
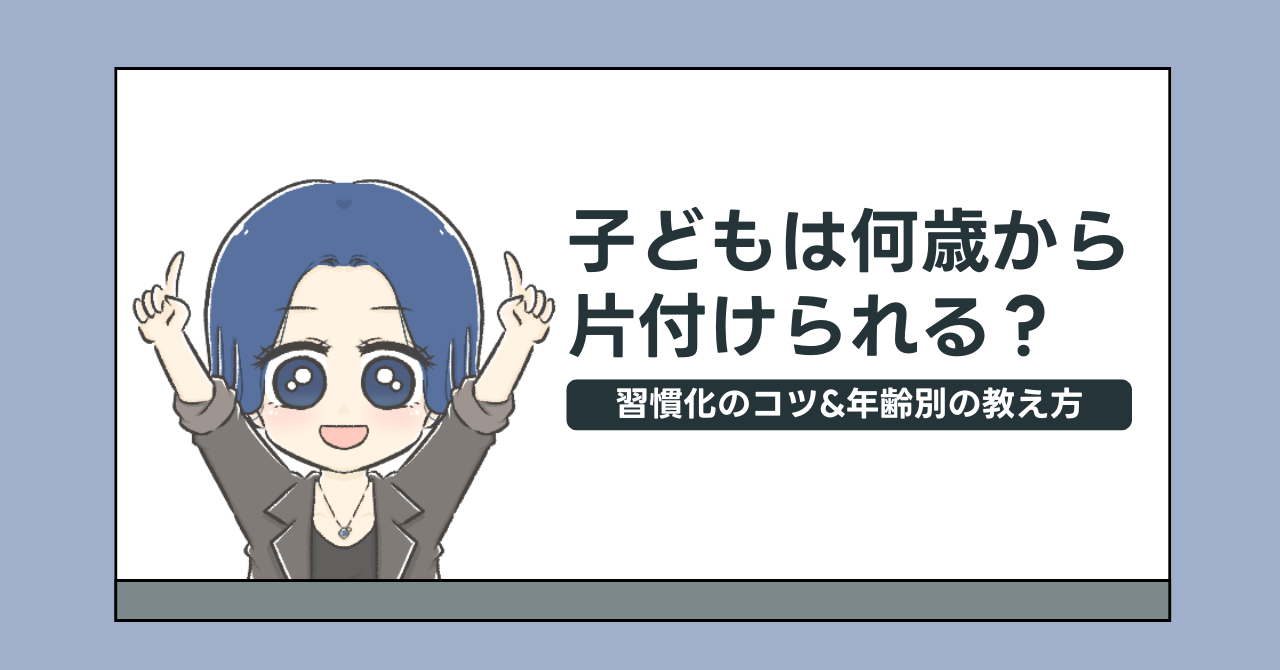
 あなた
あなた子どもって、何歳からおもちゃを片付けられるの?
こんな疑問を感じたことはありませんか?
実は、片付けの始めどきは1歳半ごろから。
ですが、本格的に「自分で片付ける」ことを理解し、習慣として身につけられるのは3歳ごろが目安です。
この記事では、年齢別の片付けスキルや、子どもが楽しく学べる工夫、親の声かけのコツまで幅広く解説します。
今日からできる小さなステップで、お片付け上手な子どもを育てていきましょう。
本記事の執筆者
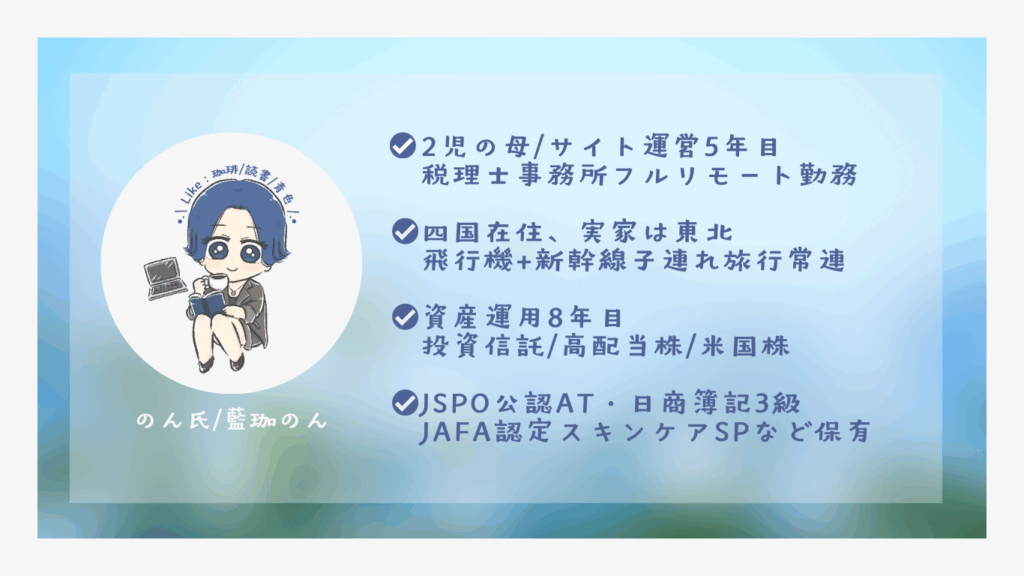
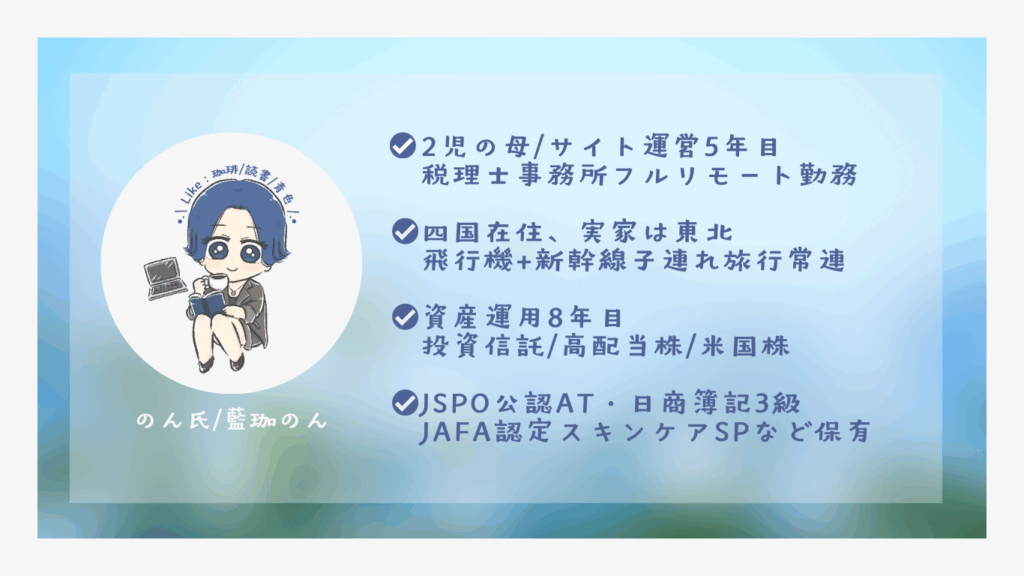
Twitter:のん氏(@aika_nonshi)
子どもは何歳からおもちゃを片付けられるのか?
子どもが自分でおもちゃを片付けられるようになる年齢は、一般的に3歳ごろが目安とされています。
- 1歳半ごろから簡単なお片付けの真似は可能
- 2歳を過ぎると簡単なタスクを任せられるように
- 3歳ごろには「遊んだら片付ける」の流れが理解できるようになる
- 4歳になると自分のスペースを意識した片付けもできるようになる
このように、発達に応じて段階的に取り組むことが大切です。
それぞれ解説していきます。
1歳半から始めるお片付けの基礎
1歳半ごろの子どもは、親の動きを見て行動を真似する力が芽生えます。
理由は、視覚や聴覚の刺激から行動を学習する時期だからです。
例えば、親がおもちゃを箱に入れている姿を見せると、子どもも真似して同じことをするようになります。
この時期はまだ理解が浅いため、「一緒にやってみようね」と声をかけながら親が主導で進めることがポイントです。
その姿勢が、「片付けってこうやるんだ」と感覚的に学ぶ土台になります。



この段階では、できたことをたくさん褒めてあげてくださいね。
2歳を過ぎると簡単なタスクを任せられるように
2歳ごろになると、子どもは少しずつ「自分でやりたい」という気持ちが芽生えてきます。
理由は、自己主張や好奇心が強くなり、周囲の行動を真似したいという意欲が高まるからです。
たとえば、「このブロックをおうちに戻してみようか?」といった簡単な指示であれば、子どもは喜んで取り組むようになります。
また、「ママと同じようにやってみようか」と声をかけることで、親と一緒に行動する楽しさが加わり、タスクをスムーズにこなせるようになります。
この時期は、成功体験を積ませることが非常に大切です。
「じょうずにできたね!」と声をかけてあげることで、子どもは「自分でできる」という自信を育てていきます。



はじめはうまくいかなくても大丈夫です!失敗しても温かく見守りながら、楽しんで取り組めるようにしてみてくださいね。
3歳から「自分で片付ける」を意識させる
3歳を過ぎると、子どもは「使ったら戻す」という概念を理解できるようになります。
なぜなら、言葉の理解力や論理的思考が発達してくるからです。
具体的には、「ブロックを遊び終わったら、ここに戻すんだよ」と教えることで、子ども自身が一連の流れを理解できるようになります。
また、片付け場所を分かりやすくラベリングすることで、子どもが自分で戻しやすくなります。
このころから、子どもが選んだものは自分で片付けるという習慣づけが可能になります。
少しずつ「自分でやる」経験を増やしていきましょう!



とはいえ、この時期はまだまだ個人差が大きいです。我が家の4歳児も、できたりできなかったりとまちまちです。個人的には、あまり慌てず成長を見守るのが1番かなと思います。
4歳になると自分のスペースを意識した片付けもできるようになる
4歳ごろになると、子どもは自分のスペースという感覚を持ち始めます。
これは、自分の物を大切にしたいという気持ちや、「ここは自分の場所」という認識が育つ時期だからです。
たとえば、「この棚はあなたのおもちゃのおうちだよ」と伝えると、子どもはそこにおもちゃをきちんと戻そうとするようになります。
また、「お友だちが遊びに来たとき、きれいなお部屋だと気持ちいいよね」といった声かけをすると、他人の視点も意識するようになり、片付けへのモチベーションが高まります。
この時期は、ルールを共有しながらも、子ども自身が判断して行動できる環境を整えてあげることが大切です。
「ここまでできたら大成功!」というゴールを決めて取り組むと、自信にもつながりますよ。



親子でルールを一緒に決めてみるのもおすすめです!
遊びと結びつけておもちゃの片付けを習慣にしよう
片付けを楽しい「遊び」のひとつに変えることで、子どもは自然と身につけるようになります。
- ゴールを決めてゲーム感覚で片付ける
- 色分けや形分けで楽しく分類する
- ごっこ遊びとして片付けを導入する
これらを取り入れることで、苦手意識を持たせずに楽しく続けられます。



とはいえ、忙しい毎日の中でこれらを常に意識することは難しいと思います。余裕がある日に、できることから取り入れてみてくださいね♪
それぞれ紹介していきます。
ゴールを決めてゲーム感覚で片付ける
子どもは競争やごっこ遊びが大好きです。
理由は、遊びながらだと集中しやすく、興味を持ちやすいからです。
たとえば、「10秒でブロックを全部戻せるかな?よーいドン!」と声をかけてみてください。
このような声かけで、片付けが遊びに変わり、子どもは自然と楽しく取り組むようになります。
また、「青いブロックは青い箱に!」と色分けゲームにすると、分類スキルも育ちます。
ちょっとした工夫で、片付けタイムがわくわくタイムになりますよ。
色分けや形分けで楽しく分類する
片付けを楽しくするコツのひとつが、「色分け」や「形分け」の遊びを取り入れることです。
理由は、子どもが色や形に強く反応する時期だからです。視覚的な違いを感じ取る力が育つタイミングで、分類遊びはとても良い刺激になります。
例えば、「赤いおもちゃは赤い箱へ」「丸い形のおもちゃはここに入れよう」といったように、ルールを遊び感覚で教えてあげると、子どもはゲームのように楽しんで片付けを始めます。
この方法は、片付けだけでなく認識力や集中力のトレーニングにもなります。
さらに、箱に色やイラストを貼っておくと、文字が読めない年齢の子でも視覚的に理解しやすくなります。
遊びながら学べる片付けスタイル、ぜひおうちでも取り入れてみてくださいね!
ごっこ遊びとして片付けを導入する
子どもは大人の真似が得意です。
その特性を活かして「お片付け隊ごっこ」や「おもちゃのおうち探し」といった遊びをすると効果的です。
例えば、ぬいぐるみに「おうちに帰ろうね」と話しかけながら片付けると、子どもも感情移入しながら片付けができます。
さらに、ロールプレイを繰り返すことで、行動としての片付けが定着していきます。
片付け=楽しい、というイメージを作っていきましょう!
声かけひとつで子どもの片付けは変わる
片付けの声かけは「命令」ではなく、「共感」や「提案」が大切です。
- 「片付けたら気持ちがいいね」と共感を伝える
- 「どっちから片付けようか?」と選ばせる
- 終わったら「きれいにできたね!」と肯定する
順番に解説します。
「片付けたら気持ちがいいね」と共感を伝える
子どもに片付けを促すとき、大人のちょっとした一言が大きな影響を与えます。
その中でも特に効果的なのが、「片付けたら気持ちがいいね」という共感の声かけです。
理由は、子どもは感情で物事を捉える傾向が強いため、「気持ちいい」というポジティブな感覚を言葉にして共有すると、行動が意味づけされやすくなるからです。
例えば、おもちゃを全部片付け終えた後に「スッキリしたね、なんだか気持ちいいね」と言ってあげると、子どもは「片付け=良いこと」と自然に認識するようになります。
このような感情の共有は、子どもの自己肯定感も高めてくれます。
注意点としては、評価や命令口調にならず、あくまでも一緒に気持ちを共有すること。
ぜひ、片付けのたびに「心が晴れるね~☀」といった表現も添えてみてください♪
「どっちから片付けようか?」と選ばせる
子どもに片付けを促すときは、命令するのではなく「選ばせる」ことで主体性を引き出せます。
理由は、選択肢を与えることで自分で決めたという意識が芽生え、やる気が高まるからです。
たとえば、「ぬいぐるみとブロック、どっちから片付けようか?」と問いかけると、子どもは「自分で選べた!」という満足感を感じながら片付けに取り組むことができます。
この小さな選択の積み重ねが、自立心や判断力の育成にもつながります。
また、片付けが進まないときにも、「先に片付けたいものから始めよう」と選ばせることで、無理なくスタートできるようになります。
親の誘導ではなく、子どもの気持ちを尊重する声かけを意識してみてくださいね。
…とはいえ、「どっちからにする?」と聞いても、「どっちも嫌!」と断られることもありますよね。
我が家の場合、そんなときは、まだ納得するまで遊びきっていないことが多いです。
朝など時間がギリギリのときは、もう片付けは後回しにしてしまい、夜寝る前に片付ける…ことも多々あります(苦笑)



子どもが小さいうちは、「どこかしらのタイミングで一瞬でも床が見えればオッケー!」くらいのメンタルでいることも大事かな…と思います(笑)
終わったら「きれいにできたね!」と肯定する
片付けが終わったあとにかける一言は、子どものやる気を次につなげる大切なカギになります。
「きれいにできたね!」という肯定的な声かけは、達成感を与えるだけでなく、自己肯定感を高める効果があります。
なぜなら、「できた」という事実を認めてもらえることで、子どもは自分の行動に自信を持てるようになるからです。
たとえば、「おもちゃを箱に戻せたね」「並べ方がとっても上手だったよ」と具体的に褒めると、より伝わりやすくなります。
結果ではなく「取り組んだこと」に注目して褒めることで、片付けそのものがポジティブな体験になります。
子どもが少しでも頑張ったときには、迷わず「すごいね!」と笑顔で伝えてあげてくださいね。



ほめほめの100倍返し~!!!
おもちゃの片付けが育てる3つの力
おもちゃの片付けは、ただの整理整頓ではありません。
- 自己管理能力
- 責任感
- 問題解決力
これらの力が自然と育つ、大切な生活習慣なのです。
それぞれ見ていきましょう。
片付けが自己管理の第一歩になる
自分のものを自分で管理する習慣は、将来の時間管理や計画力の基盤になります。
理由は、毎日続ける中で「自分のものをどう扱うか」を考えるようになるからです。
たとえば、「このブロックはここに置く」と自分で決めて片付ける経験が、自己決定力にもつながります。
子どもに「自分の持ち物は自分で責任を持つ」という意識を持たせる最初のステップとして、片付けは非常に効果的です。
小さなことから、少しずつ積み重ねていきましょう!
片付けを通じて責任感が芽生える
「自分で出したおもちゃは、自分で片付ける」というルールを通して、子どもは行動と結果の関係を学びます。
なぜなら、自分がやったことには結果が伴うということを実感するからです。
具体的には、「出しっぱなしだと遊ぶ場所がなくなる」「お友だちがけがをするかもしれない」といった気づきが生まれます。
こうした小さな経験の積み重ねが、社会的ルールや思いやりの気持ちを育てていくのです。



日々の生活の中で責任感も鍛えられるお片付け…一石二鳥ですね♪
問題解決力を育てるチャンスにもなる
片付けの中で「どうすれば早く終わるか」「どこに入れたらいいか」と考えることは、問題解決の練習になります。
理由は、試行錯誤する過程で「考える力」「やり遂げる力」が鍛えられるからです。
たとえば、「このおもちゃが入らないから、先に小さいものを入れよう」と工夫するようになります。
これは生活全般に活きるスキルであり、将来のトラブル対応にも役立ちます。



子どもが小さいうちは、親がお手本を見せたり一緒にやってあげるのがおすすめです!
子どもに片付けを習慣化させるには?
片付けは一度教えれば身につくものではありません。
- 生活の中にルールとして取り入れる
- 子どもが片付けやすい環境を整える
- 継続できる仕組みを作る
この3つがポイントです。
ひとつずつ解説します。
片付けの時間をルーチンに組み込む
毎日決まった時間に片付ける習慣を作ると、自然とルール化されていきます。
理由は、「やるべきこと」として定着しやすくなるからです。
たとえば、「夕飯の前」「寝る前」に片付ける時間を決めることで、生活リズムの中に組み込むことができます。
また、「片付けたら次の楽しみが待ってる」という仕組みにすると、やる気も出やすくなります。
ルールは、毎日の積み重ねで習慣になりますよ。



我が家では、歯磨き→お片付け→絵本といったルーティンにしています♪
絵本大好きな息子にとって、何よりのご褒美…になっているといいな~
子どもが片付けやすい環境を整える
環境が整っていないと、子どもは片付けのしようがありません。
たとえば、大人目線で棚が高すぎたり、収納が複雑すぎると、やる気がなくなってしまいます。
そのため、子どもの手が届く位置におもちゃを置いたり、ざっくりと分けられる大きな収納を使うことが効果的です。
「おもちゃはこの箱に入れるだけ!」のように、片付け方が明確であれば、子どもはどんどん自主的に動けるようになります。



我が家は引き出しや箱におもちゃをどんどんいれるだけにしています♪細かい分類はほとんどなく、トミカ・プラレール・他ハッピーセットなどといったざっくりな分類です!
維持のコツは「一緒にやる」こと
片付けが習慣になっても、継続はなかなか難しいものです。
そんなときは、親が一緒にやることで、片付けが楽しい時間になります。
また、前述の通り「きれいになったね!」と声をかけることも大切です。
とはいえ、やる気が無くなってしまうこともあるでしょう。
そんなときは、「壊れないようにおもちゃを守るんだよ」と目的を伝えることで、お片付けへの意欲が湧いてきます。



日々の声かけや関わりが、習慣を支えてくれますよ。
まとめ:子どもにおもちゃの片付けを教えるためのポイント
子どもにおもちゃの片付けを教えるには、年齢や発達段階に合わせたアプローチが大切です。今回の内容を振り返り、実践に役立つポイントをまとめました。
- おもちゃの片付けは、1歳半ごろから親と一緒に始められる
- 3歳以降は「自分で片付ける」ことを教えるチャンス
- 片付けは遊びと結びつけると楽しく習慣化しやすい
- 声かけは命令ではなく、共感や提案が効果的
- おもちゃの片付けを通して自己管理・責任感・問題解決力が育つ
- 日常のルーチンに組み込み、毎日少しずつ取り組むことが習慣化のカギ
- 子どもが片付けやすい環境を整えて自立をサポートする
- 維持のためには、親子で一緒に取り組む時間がとても重要
お片付けは単なる家事ではなく、子どもの成長を支える貴重な教育の機会です。
焦らず、楽しく、少しずつ取り組んでいきましょう♪



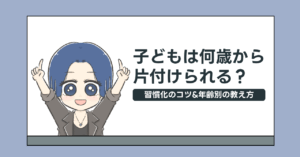
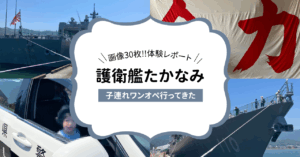
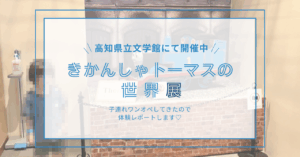
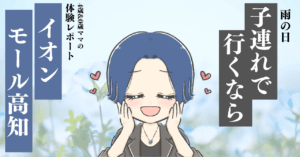
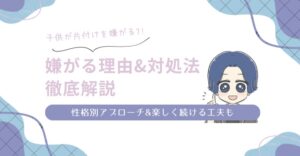
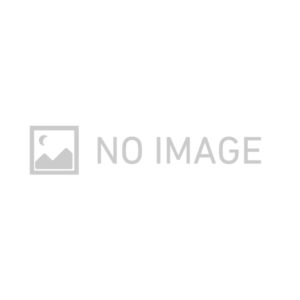



コメント